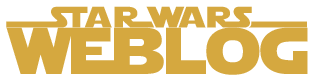「『ジェダイの帰還』で、建設中のデス・スターを破壊するのはひどい。だってあの中には大工さんや建設業者がいっぱいだったに違いないじゃないか!」
これはケビン・スミスが監督したボンクラコンビニ店員映画『クラークス』のセリフ。
はるか彼方のコンビニにたむろするボンクラが心配した通り、帝国の最終兵器デス・スターには多くの建設作業員に医者、図書館長、カンティーナの経営者に用心棒、脱獄囚、そしてもちろんトルーパーにパイロット、砲術手など様々な人々が暮らしていた。志願した者や、自分の意思でここにいるわけではない者から、彼らがデス・スターで営む仕事も様々である。
本作は、そんなデス・スターという銀河を揺るがした一大プロジェクトの渦中にいた人々の群像劇。
デス・スター建造の真っ只中から始まった物語は、無関係に思える1人1人の登場人物たちがしだいにつながりを持ち始め、やがて銀河大戦の転換期となる出来事に向かって流れていく。
時間軸が『新たなる希望』に突入すると、おなじみのあのシーンを帝国サイドから見ることができ、新鮮に感じる。特に、ベイダーがレイアと対面した時、オビ=ワンと対決した時の心理描写は興味深いものがある。
それなりに良い生活を送っていたステーションが、何十億人もの気が遠くなるような人々を虐殺するようになると、彼らはある決断をするのだが、実は物語序盤から登場しているものの、最後まで他の人物と関わらなかったキャラクターがいる。
それはスーパーレーザーの引き金を引いた張本人のデン・グラニートだ。
彼は銀河一の大砲が撃てると勇んでこの任務に就くが、1つの惑星・文化・文明・そこに住む者の生命や未来を一瞬で消し去るという恐るべき行為をその手で行うことで、取り返しが付かない苦悩に陥る。
もはや、1個人ではどうすることも出来ないほど巨大化した「軍隊」や「国家」の持つ力の恐ろしさ。
数え切れない未来を奪った、現実にある「死の星」を想起させられる一方で、中にいる人々は完全な悪ではなく、消された星の人々と同じように日常を過ごしているのもまた、SFファンタジーにリアリティを持たせている。